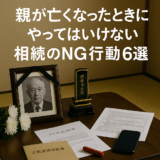子どもの進学に必要な学費は、幼稚園から大学まで合わせると1,000万円を超えるとも言われています。
しかし、「いつ・いくら・どう準備するか」によって負担感は大きく変わります。
この記事では「残された時間別」に、学費の用意の仕方を解説します。
私自身、過去に大学で職員として勤務していたころはたくさんの相談がありました。
意外と多くあるのが、
「合格はしたけど学費が払えない、どうしたらよいか」
という相談。
これはちょっとさすがにお子さんがかわいそうになってしまいます。
親御さんの責任は大きいです。
しっかりと対策していきましょう!
1. 残り10年以上ある場合|時間を最大の味方にする
子どもがまだ小さいうちに「学費準備」を始められるのは、最大のアドバンテージです。
10年以上あれば、月々少額でも“複利効果”を十分に活かせます。
学資保険・積立型保険
昔から定番の学資保険は「強制的に積み立てられる安心感」があります。
解約すると元本割れのリスクがありますが、計画的に続ける家庭には有効です。
最近では「低解約返戻金型終身保険」を学資代わりに使うケースも多く、必要な時期に解約して学費に充てられるメリットがあります。
つみたてNISA・投資信託
長期スパンがあるなら、インフレに強い「投資」での資産形成も選択肢です。
つみたてNISAを使えば、月々1〜3万円でも20年で数百万円に成長する可能性があります。
教育費はインフレで上がるリスクもあるため、銀行預金よりも投資信託の方が実質的な購買力を守れる点は見逃せません。
児童手当をそのまま積み立てる
中学生まで支給される児童手当(最大約200万円)は、そのまま学費口座に移すだけで大きな備えになります。
「貯めよう」と思っても日常の出費に消えてしまうことが多いため、口座を分けて自動積立にするのが効果的です。
ポイントは「時間を味方につける」こと。
月1万円を18年間積み立てた場合、単純計算で216万円。
投資信託で年3%運用できれば約280万円に膨らみます。

「私は複利の力を軽視していた時期があり、あとで“あの時から積み立てておけば…”と後悔しました。10年以上ある人は今すぐ動いた方が、未来の自分が感謝してくれます。」
2. 残り5年程度の場合|中期の安全運用でリスクを減らす
小学校高学年や中学生のタイミングでは、大学入学までの残り時間は5〜7年ほど。
この期間は「安全性」と「スピード」のバランスを取るのが重要です。
定期預金や個人向け国債で確実に積み立て
短期的に大きなリターンは狙えませんが、元本が保証される点が最大の安心材料。
とくに個人向け国債(変動10年)は、最低0.05%の利率保証があり、銀行預金より有利になるケースが多いです。
教育ローンを“事前に調べておく”
いざ必要になった時に慌てないように、早めに教育ローンの条件や必要書類を確認しておくと安心です。
日本政策金融公庫の「国の教育ローン」は低金利かつ長期返済可能で、公立・私立どちらでも利用できます。
今はまだ使わなくても、選択肢を知っているだけで心の余裕につながります。
家計の余力を積立に回す
この時期からは「貯められる金額を一気に増やす」意識が必要です。
- ボーナスの一部を学費専用口座へ
- 副業収入や臨時収入を全額積み立て
- 高額な固定費(保険料や通信費)を見直して浮いた分を学費へ
ポイントは「もう投資で増やすより、減らさない」こと。
残り5年でリスクを取りすぎて大きな損をすれば、リカバリーする時間がありません。
安全運用と現金積立が鉄則です。

残り5年って、実際に経験すると“あっという間”です。私もそうでしたが、つい『まだ時間ある』と思ってしまいがち。投資のリスクは抑えて、とにかく“確実に準備する”に切り替えるのが賢明です。
3. 残り1〜2年の場合|即効性のある準備を優先
大学や高校の入学を目前に控え、「もう時間がない!」という段階では、長期の資産運用は現実的ではありません。
ここからは“即効性のある資金確保”にシフトしましょう。
預金の取り崩し
一番シンプルで確実なのは、これまでの貯金を取り崩して充てることです。
もし教育資金用に分けていなかったとしても、「この口座は学費専用」と決めて切り出すことで、支出を管理しやすくなります。
教育ローンの活用
学費が一度に必要なケースでは、教育ローンが有効です。
- 国の教育ローン(日本政策金融公庫):低金利で、世帯収入制限があるものの利用しやすい。
- 銀行の教育ローン:審査スピードが速く、必要額に応じて柔軟に借りられる。
特に国の教育ローンは固定金利で返済計画が立てやすいため、家計に無理なく組み込みやすいです。
親族からの援助・生前贈与
祖父母からの支援は学費準備の現実的な選択肢です。
贈与税は年間110万円まで非課税枠があるため、計画的に受け取ることで税負担を避けられます。
また「教育資金一括贈与非課税制度」を使えば、最大1,500万円まで非課税になるケースも。
ポイントは「現金をすぐに動かす仕組み」を作ること。
この時期に無理して投資に手を出すと、運用益よりも損失リスクの方が高くなります。
安全に、確実に準備することを優先しましょう。

私もギリギリでお金が必要になったことがあります。焦って高金利のカードローンに手を出しそうになった経験から言えるのは、“ローンは比べて選ぶ”のが絶対条件です。
4. すでに学費が必要になった場合|今すぐできる選択肢
入学金や授業料の支払いが“今すぐ”必要なケースでは、とにかくスピードと現実的な手段が重要です。
教育ローン(緊急対応)
- 銀行系の教育ローンは、ネット申込で最短翌営業日融資も可能。
- カードローンとの違いは金利の低さ。できる限り教育ローンを選びたいところです。
例:国の教育ローンは融資までに1〜2週間かかるため、「今すぐ必要」なら銀行系を選ぶのが現実的です。
奨学金(給付型・貸与型)
奨学金は「入学後からの支給」と思われがちですが、大学によっては入学前申込や前倒し支給が可能です。
特に給付型奨学金は返済不要なので、条件に合うなら最優先で活用しましょう。
クレジットカードの分割・リボ払い(最終手段)
支払期限に間に合わせるための緊急策としては有効ですが、利息が非常に高いため長期利用は危険です。
どうしても使う場合は「翌月までに一括返済」など短期間で完済することを意識しましょう。
大学独自の延納・分納制度
多くの大学では「授業料の延納・分納」が可能です。
支払期限前に相談すれば、1回で払う必要がなくなる場合があります。
公的ローンや奨学金よりも気づかれにくい制度ですが、最も柔軟に対応してくれるケースが多いです。
ポイントは「とにかく支払いを遅延させないこと」。
延滞してしまうと退学リスクにもつながるため、制度やローンをフル活用して必ず支払期限を守ることが第一です。

入学金の請求書が来たときのプレッシャーは本当に大きいです。そんな時は“1人で抱え込まずに、制度を調べてすぐ動く”ことが唯一の突破口になります。
まとめ|学費準備は“残り時間”で戦略を変える
学費は「いつから準備するか」で方法が大きく変わります。
- 10年以上ある場合:投資や学資保険で“時間を味方に”
- 5年程度の場合:定期預金や国債で“安全第一”
- 1〜2年の場合:教育ローンや親族援助で“即効性を確保”
- すでに必要な場合:奨学金や延納制度で“制度をフル活用”
どのタイミングでも共通するのは「焦らず、制度や仕組みを正しく知ること」。
学費は大きな金額ですが、準備の仕方を変えれば乗り越えられる壁です。

私は“お金がない”という理由で夢を諦める子どもを減らしたいと考えています。残された時間が少なくても、方法は必ずあります。まずは今日できる準備を一歩始めましょう。
いかがでしたでしょうか。
時間があればあるほど猶予はありますので、しっかりと事前準備をしていきましょう。
近々で必要となった場合は仕方ないので即金対策をしてやるしかないですね。
そのうえで、しっかりと自分自身の計画性の無さを反省し次に活かしましょう。
大切なこどもたちのためですからね。
それでは最後まで読んでいただきましてありがとうございました!