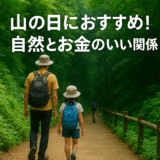はじめに|「あれ、なんか高くなってない?」の正体
2025年の夏、スーパーで「卵1パック258円」「牛乳198円」「食パン198円」という光景を見ても驚かなくなってきました。
東京都区部の最新コアCPIは+2.9%。肌感では「もっと上がってるだろ」と思う人も多いのでは?

感覚的に“ジワジワ削られてる”って人、多いと思う。家計簿つけてない人ほど実は一番やられてるんだよね
第1章|なぜインフレで「生活が苦しくなる」のか?
インフレとは、ざっくり言えば「モノやサービスの値段が上がること」。
ただ、単純に物価が上がる=悪いこと、ではありません。
問題は、“収入の伸びよりも物価の上昇が速い”ときに起こります。これが、今の日本の家計を直撃している最大の理由です。
実際、何がどれだけ上がってるの?
総務省統計局の最新データ(2025年7月 東京地区)によると
- 食料品全体:前年比 +5.2%
- パン +6.8%
- 牛乳 +9.1%
- ハム・ソーセージ類 +7.3%
- 電気代:+12.6%
- ガス代:+9.8%
- 外食費(ランチ):+5.9%
つまり、ほぼ毎日支払う“生活の基本コスト”が確実に上昇しています。

一体政府は何をしているの??
実質賃金はどうなっているのか?
厚生労働省の「毎月勤労統計」によると:
- 名目賃金(支給額そのもの)は+1.7%
- でも、実質賃金(物価を考慮した生活力)はマイナス2.1%
つまり、給料が上がってるのに生活はラクになっていないという現象が起きているのです。

政府は名目賃金が上がっていることで良しとしているけど、実態はマイナス、誰に対して政策をしているのかな?
わかりやすく言うと・・・
たとえば、こんな感じです
- 年収400万円の家庭で、月の生活費が25万円 → 27万円に増加(+8%)
- 給与は年収で+10万円上がったが、生活費の上昇により年間−24万円の赤字になる構造

これ、やばくない?給料ちょっと増えても、家賃・食費・電気代に全部もってかれて、むしろ貯金できなくなる。これが“ゆでガエル家計”ってやつだよ
家計がジワジワ壊れていく構造とは?
インフレで怖いのは、“気づかぬうちに家計が赤字化”していくことです。
特に以下の人は要注意
- ボーナス頼みでやりくりしている家庭
- キャッシュレスで支出感覚が鈍っている人
- 毎月の貯金額が“ゼロ〜数千円”の人
こういった家庭は、半年後・1年後に急な出費(冠婚葬祭・家電の故障・学費など)で破綻リスクが高くなります。
なぜ“今”インフレ対策が必要なのか?
2025年後半〜2026年にかけて、以下の動きが重なると予測されています:
- 日銀の利上げ局面が継続(ローン金利も上昇)
- 円安傾向が続き、輸入コスト増でさらに物価上昇
- 各種補助金・支援金の段階的縮小(例:電気代補助)
つまり、「来年はもっと厳しくなる」可能性が高いのです。

“いつかやらなきゃ”は“いまがその時”なんだよ。家計の防衛って、戦争じゃないけど“準備してた人”が勝つ世界
この章のまとめ
- インフレとは、“お金の価値が減る”ことでもある
- 賃金が上がらないのに生活費が上がれば、“実質的に貧しくなる”
- 今の日本は、まさにその状態に近づいている
- 家計破綻を防ぐには、今すぐ対策を始めることが重要
第2章|固定費の見直しが最もコスパがいい理由
インフレ下で「何を削れば効果的か?」と考えたとき、まず手をつけるべきは固定費です。
なぜなら、変動費(食費・交際費)と違って、一度見直せば自動的に毎月の出費が減るからです。
そもそも“固定費”とは?
- 家賃/住宅ローン(契約で固定)
- 通信費(スマホ・ネット)
- 保険料(医療、生命、火災、学資など)
- 水道光熱費の基本料金
- サブスクリプション(月額サービス)
“毎月自動的に出ていくお金”=固定費と考えればOKです。
固定費を削るメリット
- 一度やれば、毎月勝手に節約される(脳のリソースいらず)
- 効果が大きい(月5,000〜30,000円も可能)
- 精神的にラク(「我慢しない節約」)

節約っていうと“おにぎり作る”とか“水筒持ち歩く”イメージあるけど、正直めんどい。でも固定費の見直しって、一発で月1万円減とかあるんだよね。これ、バカにできん!
実例1|保険の見直しで月7,000円減!
【ケース】共働き夫婦+子1人、月収合計45万円、保険料:2.3万円/月
- 【変更前】大手保険会社で、死亡保険+医療+学資保険の3本立て
- 【変更後】掛け捨てのネット生命(例:楽天生命、ライフネット)、共済(CO-OP)に一本化
→ 月額:16,000円 → 8,500円に減少
→ 年間:90,000円以上の節約!
✅ 実例2|通信費で年間72,000円の差!
【ケース】スマホ2台(夫婦用)+光回線
- 【変更前】大手3キャリア+大手プロバイダー=月14,000円
- 【変更後】楽天モバイル+mineo+NURO光乗り換え=月8,000円
→ 月6,000円減 → 年間:72,000円の浮き

格安SIMに変えたら“通信速度遅そう”って言われたけど、今の格安は“メイン使い”でも全然OKだよ。ちなみに、我々も楽天モバイルの代理店をしてますので、お気軽にご相談ください。押し売りなどは一切しませんので、お気軽に!
見直し漏れがちな固定費リスト
| 見直し忘れがちな固定費 | 対策例 |
|---|---|
| 火災保険・地震保険 | ネット型に切替・補償の重複確認 |
| 車の任意保険 | 走行距離に応じたプランへ変更 |
| 有料アプリ課金 | 使ってないものを洗い出して即解約 |
| Amazon・Netflix等 | 家族でシェアしているか見直す |
固定費見直しの“あるある失敗”とは?
- 「手続きが面倒」と後回しにする
→結局1年放置で12万円損してる可能性も! - 「保険を切る=不安」と思い込む
→内容が重複していたり、実は過剰保障なことも多い - “見直ししたつもり”で終わる
→見積もりだけ取って契約せず終わるパターンが多い

見直しって、“やるぞ”じゃダメで、“今やる”じゃないと意味ないんだよね。10分で見積もりだけでも取ってみ?それだけで“やる気スイッチ”入るよ
見直しで得た“浮いたお金”の使い方が重要
せっかく固定費を削減しても、そのお金が「コンビニでちょこちょこ使われて消える」では意味がありません。
浮いたお金は以下のように使いましょう。
- 自動積立で貯金 or 投資へ
- 子どもの教育費口座に自動送金
- “体験消費”に使う(旅行・ワークショップなど)

防衛だけじゃなく、“お金を味方につける行動”がセットになると、家計はマジで変わる。浮いたら“使わない”んじゃなくて“活かす”。あとは、切り詰めるだけではなく、学びや体験に使って自己投資も大切ですね!
まとめ:固定費の見直しは「やったもん勝ち」
- 毎月勝手にお金が浮く=心理的負担ゼロ
- 保険・スマホ・ネット・サブスクの4点はすぐ見直し可
- 見直したら“浮いた分”の使い方までセットで設計!
第3章|“買い方”を変えるだけでインフレに勝てる
節約というと「我慢する」イメージが強いですが、インフレ対策においては“賢く買う”=戦略的な消費行動が非常に効果的です。
なぜなら、今の物価上昇は「一律の大幅値上げ」ではなく、「ある商品だけが高くなっている」「同じ物でも場所で価格が違う」など、“バラつき型インフレ”だからです。
1. 食費の見直し:買う場所とタイミングでこんなに変わる!
【実例:牛乳(同じメーカー)】
- コンビニ:218円(税込)
- 大手スーパー:178円
- 業務スーパー:158円
- 地元の農協直売所:148円(しかも低温殺菌でおいしい)
これ、週2本×年間で7,000円以上の差になります。
▶︎ コツ:
- 「近い」より「安い」を選ぶ日を週1つくる
- まとめ買いは空腹時を避ける(ムダ買いが増えるため)
- ポイント還元日・クーポン日を事前にチェックする

俺、最近“火曜市”のリズムできたんだけど(笑)、これあるだけで“買い物スケジュール”が固定されて、ムダな買い足しも減るんだよね
2. まとめ買いדフードロス対策”で節約とエコが両立
- 賞味期限間近の商品:半額や30%OFFが当たり前
- 見切り品の野菜:味はほぼ変わらず、カレーや煮物で活用可
- 大容量パック:冷凍保存やシェア買いすればコスパ◎
▶︎ 具体テクニック:
- お肉は100g単価が安い“塊肉”を買って小分け冷凍
- ごはんは炊飯後すぐに100gずつ冷凍しておくと、外食率が激減
- 「1日1冷凍消費DAY」を設けて、ロスゼロ化
あとは、別の記事でご紹介した、お買い得なサイトを活用することもおすすめです!
3. 日用品・消耗品は“インフレ見越し”で戦う
消費者庁によると、2025年6月までにトイレットペーパー+9.7%、洗剤+8.3%、ティッシュ+7.4%の値上がりが報告されています。
▶︎ インフレ下での対処法:
- 【戦略買い】:ドラッグストアの“LINE友達限定クーポン”を併用
- 【在庫リスト化】:日用品の“残量チェック表”を冷蔵庫に貼る
- 【共同購入】:コストコを活用してママ友や近所で“まとめ買い→山分け”もあり

俺はもう“紙モノは月1で一気に仕入れる”って決めてる。ティッシュもトイペも“余ってる時”に買うのが一番安く済むのよ。あとは、ふるさと納税とか、株主優待とかも活用している!
4. “店”より“アプリ”を活用せよ
今はリアル店舗でもアプリで割引・ポイント加算が主流。
例えば
- トクバイアプリ:近所の特売情報が即見れる
- 楽天ポイントカード:対象店舗での買い物で1〜3%還元
- PayPayクーポン/dポイントスーパー還元:最大30%オフもザラ
- LINEアカウント登録(週替わりクーポン)
- 楽天Pay or PayPay支払い+クレカ紐付けでポイント3重取り
5. 買い物ルールを“見える化”すると、勝手に節約される
無計画に安いから買うと意外に失敗します!そうならないためにも・・・
- 【例】「1週間で3,000円しか使えない日用品予算ルール」
→ “使える額”が決まっていると、買い物中の判断がブレない - 【例】「1人で買い物に行かない」
→ 家族や子どもと一緒に行くと無駄買いが増える傾向あり(特にお菓子)

俺、昔“今日特売だから買っとくか”がクセになってて、気づいたら冷凍庫パンパンだった(笑)節約って“ルール化”が鍵!
よくある“節約ミス”もチェック!
安いから買うと「安物買いの銭失い」という落とし穴もあります!
- 安さにつられて“必要ないモノ”まで買ってしまう
- 「ネットの方が安い」は送料やタイムロスで逆転することも
- クーポンを使うために“余計な買い物”をしてしまう
→「節約目的」だったはずが、「出費を正当化」するマインドに変わると本末転倒です。
まとめ:買い方=“お金の使い方の戦略”である
- 買う場所・タイミング・量を変えるだけで、年間数万円の差が出る
- アプリ・セール・まとめ買いは3種の神器
- 自分のルールを1つ決めて、まずは「1週間」やってみることが大事!

あと個人的におすすめなのはファスティング!理由は、断食して体から毒素を排出して健康的に、しかも断食をするから食費も若干節約になります。これは1粒で2度おいしいんです!(笑)
第4章|“稼ぎ”もインフレ対策になる
節約だけでは、限界がある。
なぜなら「削れるものには、削りしろの限界がある」から。
一方、“稼ぎ”は上限がない。特に今のような物価上昇=お金の価値が下がる時代には、稼ぐ力を育てること自体が最大の防御になります。
インフレ時代は「円」の価値が目減りする
物価が5%上がれば、100万円の現金は実質95万円の価値に。
つまり、“預金してるだけで損をしている”状態になるわけです。

俺も昔、“貯金は美徳”って思ってたけど、それって“減ってく資産にしがみつく”ってことだった。今は“攻めて守る”時代だと思ってる
「本業+α」で生活防衛する4つの方法
1. フリマ・不用品販売(月1万円〜)
- メルカリ/ラクマ:子ども服・使わない家電・本・雑貨など
- 「季節の変わり目」「引越し前後」は特に狙い目
参考:
・1品1,500円×10点で15,000円
・送料と手数料を引いても約10,000円が残る
2. スキルシェア・副業サービス(月1〜5万円)
- ココナラ/タイムチケット/クラウドワークスなど
- 文章作成/資料作成/SNS運用/Excel整備/話し相手 など多様なジャンルあり
- 「手に職がない…」人でも、“事務経験”や“接客スキル”で稼げる時代

副業は基本的にバレません!本業先の会社で副業を禁止されてても、かまわずやりましょう!私はガンガンやってました!
3. 収益化SNS・情報発信(月数千〜数万円)
- X(旧Twitter)で商品紹介(アフィリエイト)
- noteで体験談記事を販売
- YouTubeやTikTokで発信→収益化
身近な例としては、、、
- 「家計簿晒しアカウント」で月3万円の収益
- 「株主優待」の記事が10本売れて1万円
4. 投資(NISA/保険/クラウドファンディング)
- つみたてNISA・新NISA:長期インフレに強い資産形成の基本
- 変額保険:インフレ対応型の保険運用ができる商品も
- 不動産クラファン(例:CREAL、Jointo α):1万円〜でも家賃収入的な投資が可能
注意:
・短期で増やそうとしない(元本保証なし)
・「目的のある運用」がポイント(老後、教育、FIREなど)

俺、保険と不動産、株、債券を組み合わせて“老後資金は放っておいても増える仕組み”にしてる。最初は怖かったけど、勉強すれば見える世界が変わるよ!FIREできたのも、勇気をもって行動したから!
「時間をお金に換える」から「仕組みを持つ」へ
副業も、最初は“時間を切り売りする”形からスタートしてOKです。
でも、最終的には“仕組み化”がインフレ時代の家計を守ります。
例えば・・・
- 自分のスキルをマニュアル化→note販売や教材化
- フリマ販売の“テンプレ返信文”で工数削減
- SNSでファンを育てて「選ばれる人」に

副収入は“稼ぎ”というより“安心材料”なんだよね。“いざとなれば俺にはコレがある”って思えると、心にゆとりが出る。それが一番の資産かも
まとめ:収入の柱を1本増やすだけで防御力は段違い
- 「稼ぐ力」はインフレに最も強い“防御と攻撃”の両輪
- 難しいことは不要。“できることから1つだけ”やる
- 習慣化すれば、副業はストレスではなく「自信」になる
第5章|お金を“見える化”するだけで、浪費は減る
「節約したいなら、まずは家計簿をつけろ」
昔からよく言われることですが、実際にやっている人は少数派。でも実はこれ、インフレ時代には特に最強の家計防衛テクニックなんです。
なぜ“見える化”で浪費が減るのか?
人は、「見えるものに注意を向ける」という性質があります。
心理学ではこれを「注意のバイアス(attention bias)」と呼びます。
つまり
❌ “何にいくら使ったか思い出せない”
→ 無意識にムダ遣いが増える✅ “今月あと5,000円しか使えない”
→ 自然と支出を抑えるようになる

昔“感覚派”で家計簿とか絶対無理だった。でもレシート集めて“赤ペンで合計”しただけで“え、俺コンビニ1万円使ってる!?”って衝撃だった(笑)
超カンタン!家計“見える化”3ステップ
▶︎ ステップ1:レシートを1週間ためる
財布やスマホケースに入れるだけでOK。
“何をどこで買ったか”を行動の記録として残すことが第一歩。
▶︎ ステップ2:支出ジャンルに分けて合計
以下のような分類でOK:
- 食費(外食含む)
- 日用品
- 子ども関連
- 交通費
- 交際費(コンビニやカフェも含む)
- その他(雑費)
→ 1ジャンルでも「え、こんなに?」と気づけばOK!
▶︎ ステップ3:「週予算」を決めてみる
月ベースより、週単位の方が“ブレにくく継続しやすい”です。
例:食費15,000円 → 週3,500円×4週+残り1,000円は外食用
家計簿アプリも使ってOK(ズボラでも続くやつ)
📱 おすすめアプリTOP3
- マネーフォワードME
銀行・クレカ・電子マネー自動連携、超優秀!
→ 一目で“今月いくら使ったか”が分かる - Zaim
レシート撮影→自動分類が便利。初心者向け
→ 食費や日用品の割合がグラフで見える - OsidOri(オシドリ)
夫婦やパートナーと家計共有できるアプリ
→ 共働き家庭や育児中夫婦におすすめ

俺は“自分で打ち込むのは無理”だから、最初は“レシート撮影して放置”から始めたよ。勝手にグラフになってて、笑った(笑)
“見える化あるある”失敗パターン
- 「1円単位で細かくつけようとして挫折」
- 「見たくない現実に落ち込んでやめる」
- 「アプリを入れただけで満足」
→ 解決策は:完璧を目指さず、まずは「気づくこと」だけに集中する。
習慣化するコツ
- 朝コーヒーとセットで10分“家計見返しタイム”
- レシートを冷蔵庫に貼って“視覚刺激”にする
- “月末家計棚卸し”をSNSで発信して強制力を持たせる

朝にコメダで5分読書+家計見直しってルーティンにしたら、習慣になったよ。場所と時間を固定するのがコツ!
見える化したあとの“アクション”が重要!
記録だけして終わる人が多いけど、重要なのはそこからの“改善行動”。
- コンビニ3,000円 → ドリンクだけマイボトル化
- 外食費15,000円 → 週1弁当にして月5,000円浮かせる
- 定期購入を一度見直す → 年間1万円の見直しもザラ
まとめ:見える化は家計防衛の“最初の一歩”
- 使い方に“意識の光”を当てるだけで無駄が減る
- 細かさより「気づくこと」が目的
- 無理せず、まずは“記録してみる”から始めよう!

節約しようとするより、“数字を見て自分のクセに気づく”ほうが100倍効果ある。見える化って、自分の浪費と向き合う“最強の武器”だと思う
第6章|子どもに“思い出の価値”を伝えるチャンス
インフレでレジャー費が削られがちな今こそ、「体験が記憶になる」ことの価値を再確認すべきタイミングです。
特に子どもにとっては、高価なモノよりも、“誰と・どこで・どんなふうに過ごしたか”が将来の記憶として残るという研究もあります。
お金がかからなくても“記憶に残る体験”は作れる
国立青少年教育振興機構による調査では、「心に残っている体験」に挙げられた上位項目は以下の通り
- 家族と食事を作った
- 公園で虫取り・水遊び
- 地元の祭りや花火大会
- 図書館での読み聞かせや夏の催し
→ どれも1,000円以下 or 無料でできるものばかり!

うちの社団法人でも“500円の寄付から夏の思い出を届ける”寄付プロジェクトをやってるけど、実際“お金じゃなくて、親子の時間”なんだよね。一緒に笑った記憶が、宝物になる
私たちが取り組んでいる、「すべての子供たちの体験格差を解消する!」というテーマで活動している、一般社団法人親子Mirai Canvasでは、非営利型の事業組織として、無償でこどもたちにイベントを通じて、学び、遊び、体験をプレゼントしています!
よかったらサイトをご訪問くださるとうれしいです!
おすすめ!低予算で実現できる親子体験アイデア
▶︎ 地元の“無料イベント”を活用
- 公共図書館の「夏休み自由研究お助け講座」
- 市町村の広報誌に載っているイベント(縁日、盆踊り、花火など)
- 小学校のグラウンド開放や学校主催の夕涼み会
地域の掲示板、図書館、役所のHPを週1でチェック!
▶︎ おうち時間を“冒険”に変える工夫
- リビングにテントを張って“おうちキャンプ”
- 親子でゼリーやたこ焼きなど“屋台風スイーツ”を手作り
- 「今日は君が先生!」親子逆転で工作or読書感想を発表会
- 段ボールで秘密基地/お店ごっこ
→ 費用は500円以下でも「記憶に残る体験」になる!

要するに、知恵と工夫でどうにでもなるっていうことですね!
“体験の格差”が“自己肯定感の格差”になる前に
令和5年度の文部科学省調査では、「経済的に厳しい家庭の子どもほど、体験の機会が少なく、自己肯定感も低い傾向」があることが指摘されています。
でも、これは逆に言えば──
「体験さえ与えられれば、心は豊かに育つ」という証拠でもあります。
親のメンタルにも“共通体験”は効く
- 子どもと一緒に笑うと、親のストレスホルモン(コルチゾール)が低下する
- 子どもの「ありがとう」で、自己肯定感・育児満足度が上昇する
つまり、親子の体験は“子どもの成長”だけでなく“親自身の癒し”にもつながるんです。

私がFIREして最初に感じたのって、“自由なはずなのに虚しい”だった。でも親子でイベントしたり、笑い合ったとき、“あ、これが本当の豊かさだな”って思ったよ
思い出は“資産”になる
- お金は使えば減る。でも、思い出は増えるたびに「幸せの残高」が増えていく
- 将来、子どもがふとした時に思い出す「宝物」になる
これは、どんな保険にも預金にも代えられない、“心の資産形成”です。
おわりに|「変化に適応する力」が最大の資産
2025年の今、インフレはもう“一時的なもの”ではなく、私たちの生活に定着しつつある環境変化となっています。
でも恐れる必要はありません。なぜなら、「変化」はいつの時代にも起きてきたことだからです。
大事なのは、「どう対応するか」。
節約ではなく“戦略的削減”を意識する
ただ我慢するだけの節約は、精神的にも限界があります。
でも、“無駄を仕組みで削減する”ことはストレスも少なく、効果が持続します。
- 保険や通信費など「一度やれば効果が続く」固定費の見直し
- コンビニや衝動買いの“パターン”を自覚するだけでも支出は変わる
「削る」ではなく、「整える」。
それが戦略的削減です。
貯めるだけじゃなく“増やす”ことにも目を向けよう
預金やタンス貯金だけでは、お金の価値が減っていく今。
「どう守るか」と同時に、「どう育てるか」を考えることが、家計の未来を明るくします。
- NISAやiDeCo、変額保険など、“守りながら増やす”選択肢
- 副業・スキルシェアで“現金以外の価値”を生む行動
- 自分の経験・知識を商品化する情報発信
お金を増やす力は、「自己肯定感」と「未来の安心」を一緒に生み出します。
モノより“経験”を残す暮らしへ
値段で測れるモノよりも、記憶に残る体験や一緒に過ごす時間のほうが圧倒的に価値がある。
特に子どもとの時間は、“一生モノの資産”になります。
- 1,000円でできる親子イベント
- 近所の公園、夜の星空、手作りのおやつ
- 「楽しかったね」と笑い合える記憶
インフレ時代の家計防衛とは、「限られたお金で最大の幸福を生み出す工夫」でもあります。
マネーシールド流・生き残る家計とは?
- 削るだけじゃなく、構造を変える
- 増やすだけじゃなく、支え合う
- 守るだけじゃなく、笑い合う
数字だけにとらわれない、“家計の幸福設計”が、マネーシールドが伝えたい家計防衛の本質です。

自分は2023年にFIREして“自由になった”はずなのに、どこかで不安だった。でも気づいたんだよ。“金を守る力”があってこそ、自由って安心に変わるんだって。
まずは1つでいい。この記事の中から、“今日やれること”を、今日やってみてください!なんかあったら「どらやき1つで」いつでも相談にのります!(笑)
それでは最後まで読んでいただきましてありがとうございました!