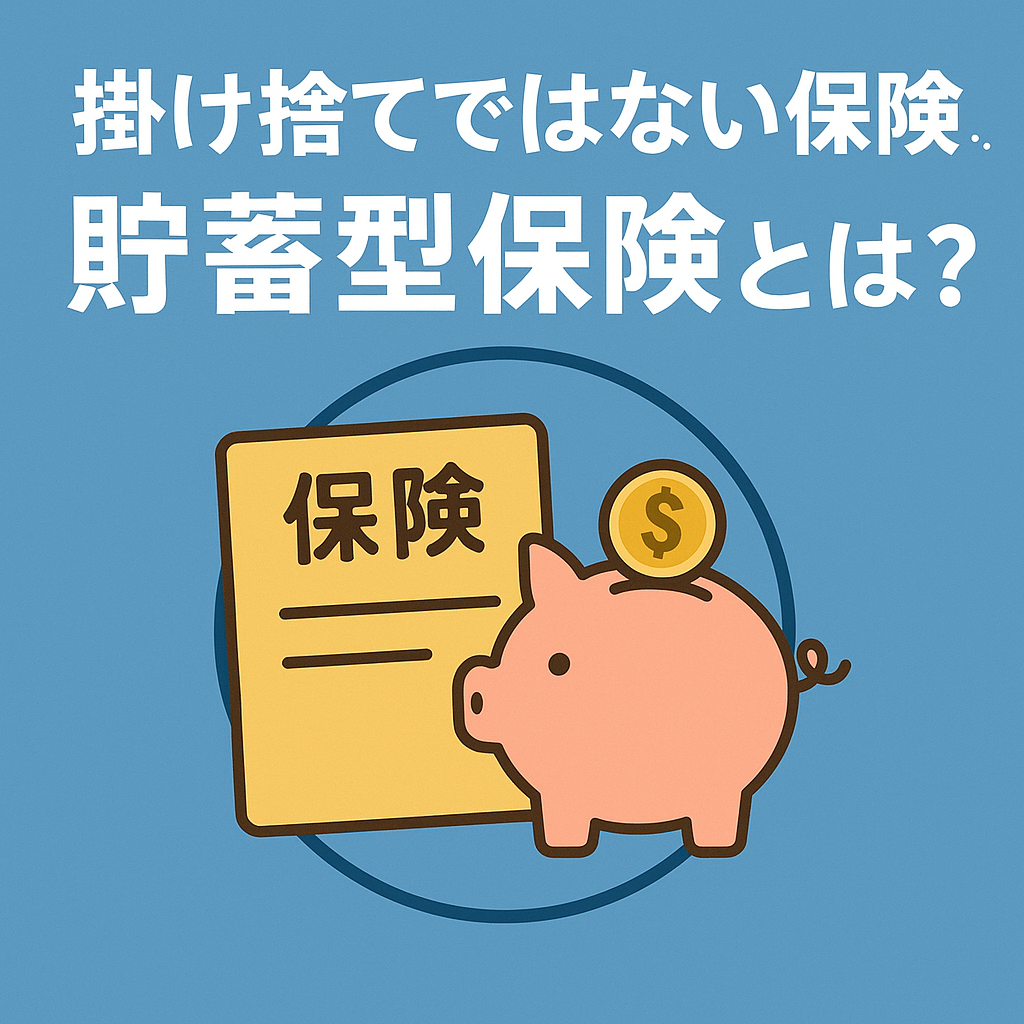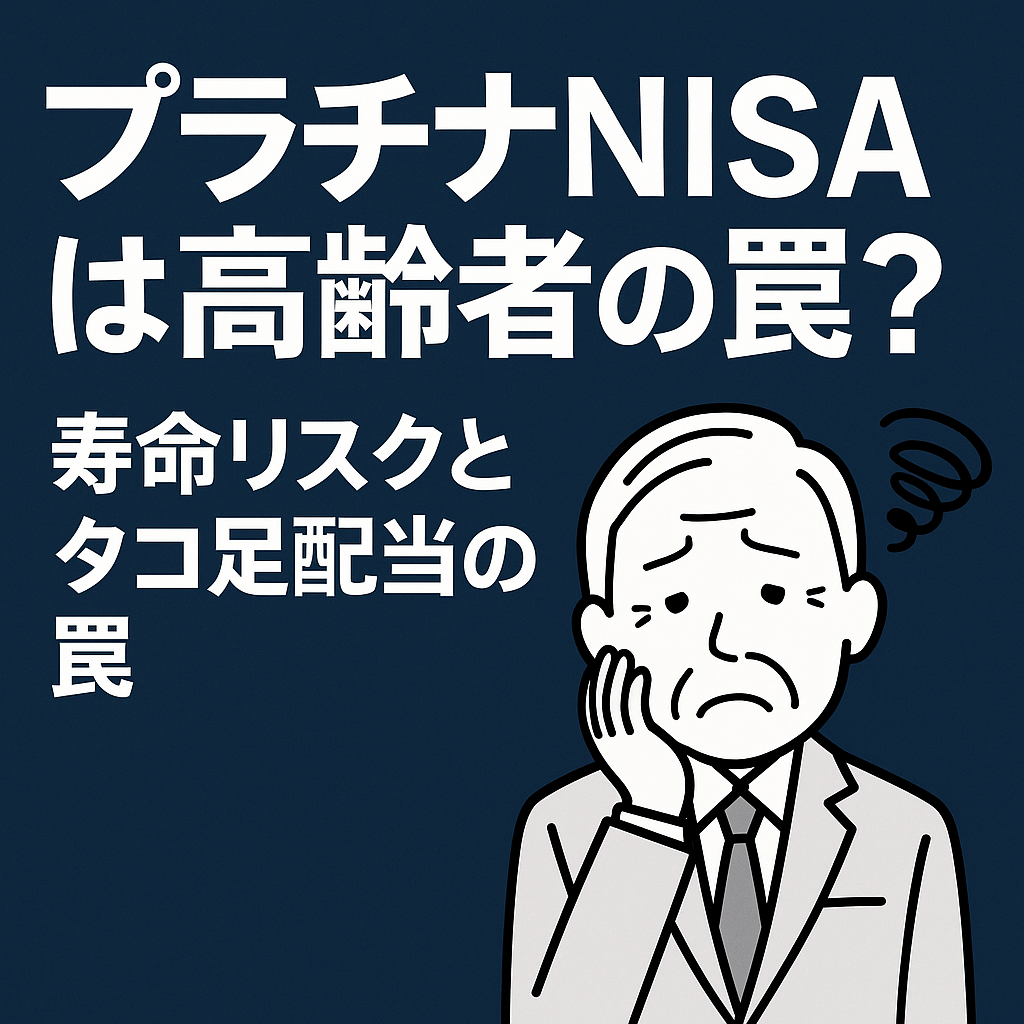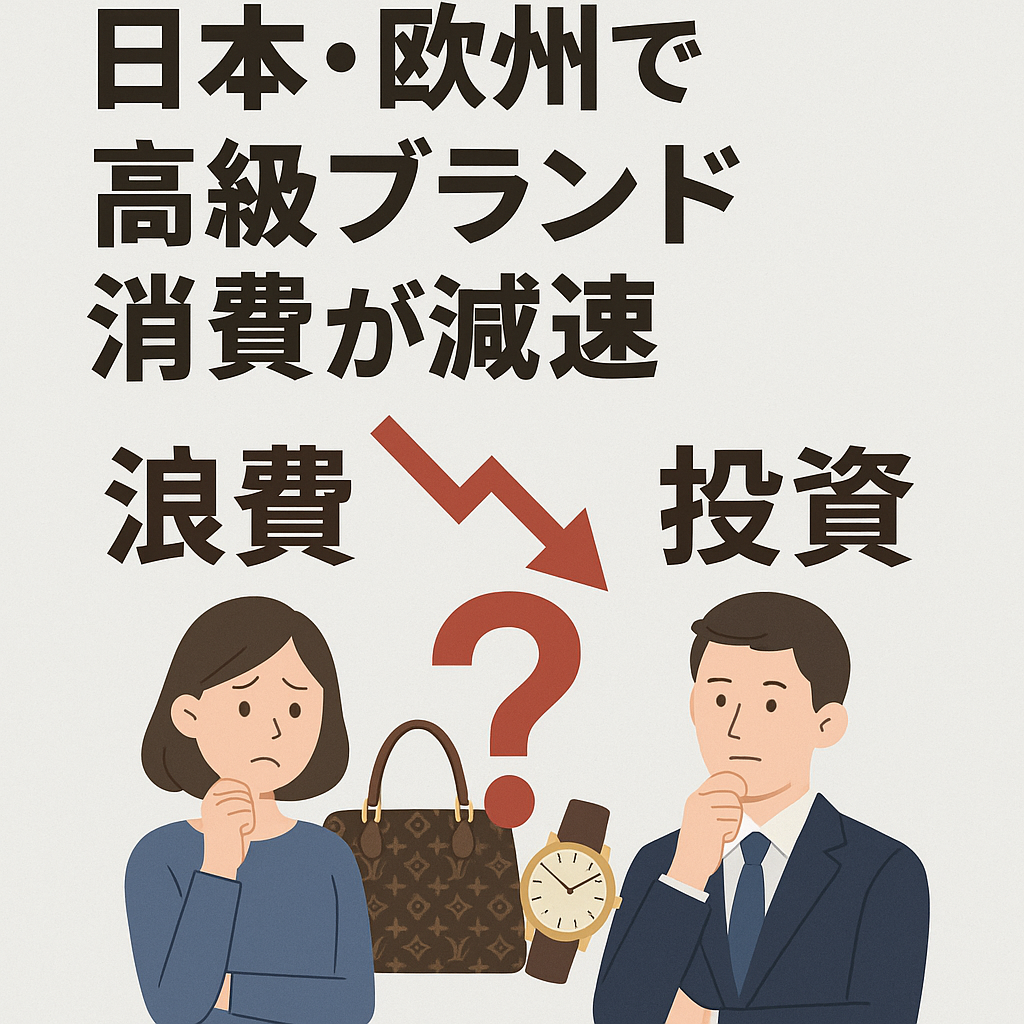貯蓄型保険とは?生命保険+貯蓄を両立できる保険商品
貯蓄型保険とは、生命保険の保障機能に加え、将来お金が戻ってくる「貯蓄」要素を持つ保険のことです。満期時や途中解約時に解約返戻金や満期保険金が支払われる仕組みで、掛け捨て型と異なり“保険料が丸々無駄にならない”のが大きな特徴です。
代表的な種類には、以下の保険があります:
- 終身保険:満期がなく、一生涯保障が続く。解約時には返戻金が受け取れる。
- 養老保険:死亡・高度障害時には死亡保険金、生存時には満期保険金を受け取れる“生死混合型” 。
- 学資保険:子どもの教育資金用。契約者が死亡した際には以降の保険料が免除され、予定どおり支払いを受けられる。
- 個人年金保険:将来の年金を準備。確定年金や終身年金などがあり、年金開始後に受け取り始められる。
メリット:保障と貯蓄、節税・貸付制度も活用できる
✅ 解約・満期返戻金がある
払込んだ保険料の一部または全額を、契約年数に応じて解約返戻金・満期保険金として受け取ることができます。契約内容によっては、支払額を上回る場合もあります。
✅ 保障機能がある
死亡時・高度障害時には、保障金が支払われます。契約してすぐに保障が効くので、貯蓄だけでは準備できないリスクへの備えができます。
✅ 契約者貸付が利用可能
解約せずに解約返戻金の範囲内でお金を借りる制度があり、急な資金需要に対応できます。ただし利息が付く点に注意が必要です。
✅ 生命保険料控除の対象
支払った保険料は税制上、生命保険料控除の対象になり、年末調整や確定申告により所得税・住民税の節税効果が期待できます。
✅ 自動積立で貯蓄が続けやすい
口座引き落としなどにより自動的に積み立てが行われるため、貯蓄が苦手な人でも継続しやすく、つい使ってしまう心配がありません。
デメリット・注意点:コスト高・元本割れ・流動性の制約
❌ 保険料が割高
掛け捨て型保険と比べて、保障+積立の分だけ保険料が高く設定される傾向にあります。同一保障額でも、掛け捨て型の方が保険料は安価です 。
❌ 元本割れリスク
解約返戻金は契約からある程度期間が経たないと払い込んだ総額を下回ることが多く、特に契約初期の解約は元本割れの可能性があります。低解約返戻金型などでは注意が必要です。
❌ 運用利回りは低め
運用利率(標準利率)は低く設定されており、預貯金や投資型商品と比べて資産運用としての利回りは決して高くはありません。
❌ インフレ耐性が弱い
将来的に物価が上昇すると、受け取る保険金の実質価値が目減りします。固定金利商品では特にインフレリスクに弱いため、現金価値が下がる可能性を理解しておきましょう。
❌ 流動性が低い
解約や貸付などしない限り現金の引き出しが難しく、自由に利用できない点は普通の預金と異なります。現金ニーズに応じた柔軟性がないことに注意が必要です。
❌ 見直しが難しい
途中解約の損失リスクがあるため、ライフステージの変化に応じた見直しがしづらい点も大きなデメリットです。
❌ 課税対象になる場合あり
満期保険金や一時金は、支払保険料総額と一定控除額との差額の二分の一が課税対象となるケースがあり、所得税や贈与税の対象にもなりえます 。
どんな人に向いているか?
以下のような方に、貯蓄型保険は向いているといえます:
- 貯蓄が苦手な人:自分で続けるより保険で積立したほうが継続できる方
- 保障と貯蓄を両立したい人:将来の子どもの教育や老後資金を準備しつつ、万が一の保障も得たい方
- 家計に余裕がある人:長期間の保険料支払いを継続できる安定した収支のある家庭
総括と選び方のポイント
貯蓄型保険は、保障と貯蓄を同時に備えたい人向けの金融商品として一定の魅力があります。ただし、保険料負担や元本割れ、流動性の低さなどの注意点を十分理解して、契約期間や支払総額、ライフプランとの整合性を見極めることが大切です。
契約前には以下の点を確認しましょう:
- 保険料の総額および返戻金シミュレーション
- 解約返戻率の上昇タイミング
- 契約者貸付制度や払済・延長保険の特約内容
- 課税処理(通常は満期や一時金時の所得税・贈与税)
- 将来的なライフイベント(子どもの進学、老後の資金計画など)との整合性
貯蓄型保険は、長期的に無理なく払い続けられる家計と、ある程度の待てる精神がある方にこそ、安心して選べる選択肢となります。気になる方は、保険商品を扱う複数の会社のパンフレット比較や、ファイナンシャルプランナーへの相談をおすすめします。
貯蓄型保険は万能ではありませんが、「保障+貯蓄+貸付+節税」といった多機能が一体になっているため、使い方次第では賢いライフプランの一助となります。あなたの将来設計にあった最適な選び方を見つけてください。
〇あとがき
貯蓄型保険といっても様々なタイプの商品があり、例えば同じ「終身保険」でも、目的や考え方によって、支払方法や支払期間、運用通貨、保障内容などは異なります。プランの内容によってはメリットを受けられない場合もありますし、デメリットを解消出来る場合もあります。教育資金にしたい人、結婚や一人暮らしの応援資金、海外旅行の費用、老後に向けて貯めたい、緊急予備資金の確保、相続対策…目的に合わせた内容になっているか、リスクは許容範囲内かを確認して契約をしましょう。
私はよく年金開始のお手続きを承りましたが、実際にお受け取りを迎えたお客様は、皆さん「もっとやっておけばよかった」「自分で積み立てた年金があるから少しは楽しめる」など、昔を思い出しながら笑顔でお手続きされていました。デメリットもありますが、自分で作った仕組みが未来の自分にちゃんと戻ってきますよ。